「おんど珈琲」の紹介と、少しの説明を。
言うまでもなく、読んで字の如く、ご想像の通り、珈琲屋さんです。
でも自家焙煎するわけでもなく、喫茶店やカフェを営業しているわけでもありません。
少し変わった珈琲屋として、スタートしました。
「おんど珈琲」の活動について(野望)
「おんど珈琲」は店舗を持たず、ケータリングやイベントなどで珈琲を淹れる活動を行います。
どこか拠点があっても良いのかなと、頭によぎることはしばしばありますが、お店を構えることはまだハードルが高く感じます。
まずは自分が出来ることから少しずつ。
とはいえ、いずれお店を構える機会があれば歓迎して取り組みます。
時期と縁を大切に、アンテナは常に張っておいて、タイミングを焦らず。
日本各地で珈琲を淹れたい
日本全国で珈琲を淹れること、そう簡単に上手くいくとは思っていません。
見知らぬ土地でいきなり珈琲を淹れることは難しい。
「おんど珈琲」として珈琲を淹れるということは、その場所に集まる人たちに飲んでもらうため。
こんな珈琲があるよ、と知ってもらうため、全国で活動したいと思っています。
「おんど珈琲」のコミュニティは、人と人との繋がりがなければ成立せず、縁のある人に誘ってもらえて、その場所で珈琲を淹れることができます。
なので、やたらめったに日本全国で珈琲を淹れる旅に出る、という意味ではありません。
結果的に、日本全国を巡った!となれば、それはとても嬉しいことです。
また、ブログを通じて、訪ねた地域やイベントの情報発信をし、場所やコミュニティの魅力を伝えます。
これが日本全国を巡りたい、もうひとつの理由です。
焙煎士やロースターと、飲む人の間に立つ、珈琲屋さんになりたい
各地の焙煎士、ロースターを訪ね、様々な珈琲を楽しめるよう活動を続けることが、夢です。
珈琲の豆は主に赤道近くの国で、うまく育ちます。
(珈琲豆の流通については、そのうち詳しく書こうと思っていますので、ここでは割愛しますね)
生豆の状態の珈琲豆を焙煎(焼くこと)し、一般的に見られるような珈琲豆が作られます。

焙煎前の珈琲豆。生豆の状態はこんな感じ。
珈琲豆は、農作物です。
農作物がゆえに、その焙煎は試行錯誤やチャレンジの連続です。
珈琲豆は気温や湿度にとても敏感。同じ生豆を同じように焙煎したとしても、同じ味を作り続けるのは大変な作業です。
(機械技術の進歩によって、味のブレは少なくなっているとのことですが)
何が言いたいかというと、焙煎士の人たちの大変な努力をないがしろにしたくない、ということ。
(・・・かといって、「おんど珈琲」が提供する珈琲に深い意味を持たせようとか、難しい話や事情の把握を強要するつもりはありません。長々と一方的に厚かましい説明もしないし、ましてや珈琲を高尚な飲み物にしたいとか、ではありません)
「おんど珈琲」は焙煎を生業としている人たちにとって「広告塔のような存在」になりたいと思ってます。
「おんど珈琲」が販売するのは、「焙煎士の作ったおいしい珈琲豆を使って、淹れた珈琲」です。
そうすることで焙煎士、ロースターの方々へ、おいしい珈琲のお礼を還元できれば、と思っています。
そのために、珈琲の知識は常にアップデートするし、ロースターの方たちからのレクチャーは積極的に受けようと思っています。
飲む人にとって、新しい珈琲の発見に
珈琲時間をさらりと楽しんでもらいつつ、こんな珈琲もあるんだと感じてもらうこと。
これが、飲んでもらった人に与えたいメッセージです。
珈琲は、仕事中、おしゃべり中、休憩中、食事中や食後など活躍するシーンやシチュエーションがとても多い飲み物です。
こういう飲み方をしなさい、と決められていないとても自由で便利な存在です。強いて言えば、寝る前は良くない、ぐらいでしょうか。
そんないつもの時間のお供や、隙間時間を珈琲時間に、あれば良いと思ってもらいたい、それがおんどが淹れる珈琲です。
おんど珈琲は、ある程度決まったロースターから仕入れることにはなりますが、おいしいと思える、縁あって出会えた焙煎士からその都度新鮮な珈琲豆を仕入れ、できるだけいろんな珈琲をみなさまに味わって頂こうと思っています。
その際、どこで買った珈琲なのか、少し説明をしたり、チラシやショップカードを渡したり、します。
そして、気に入った珈琲豆は、おんど珈琲を介さず、直接ロースターから買って自宅で淹れてみてください。
それでもきっと、おいしい珈琲が入ります。
その珈琲をさらりと飲んで、いつもの時間を過ごしてください。
そうして、ロースターと飲む人が繋がれば、嬉しく思います。
飲む人たちに色々な珈琲があることを知ってもらいたい、日本にはいろんなロースター、焙煎士がいる、という布教活動のようなことをしていきたいです。
ケータリング、イベントのお供に
個展、イベント、おもてなしの場など、珈琲ぐらいあったらいいな、と思えるように場所に呼んでもらえたら、とても嬉しいことです。
肩書きについて(仮)
バリスタという肩書きは、誰でも名乗れます。たとえ珈琲を淹れたことがなくても。
有資格者ではないので「バリスタ」と名乗りにくいのですが、ちょうど良い言葉が見つからないので、恐れ多くも「バリスタ」と名乗ることにします。
そしてお店を持たないので「出張」と付け加え、ひとまず肩書きは「出張バリスタ」。
大手コーヒーチェーン店で働いている人や、喫茶店で珈琲を淹れているバリスタよりも、おんど珈琲の方が珈琲を淹れる回数は少ないかもしれません。
でも、淹れた分、自分で飲んで味わっているし、少しの分量で変化する味や、豆の鮮度による移ろいを楽しんでいます。
このブログのこと
当ブログは「おんど珈琲」の総合窓口として作りました。
ケータリングやイベントのお誘いがあれば、お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
SNSも良ければフォローしてやってください。
Twitter、Instagram共にアカウント名は「おんど珈琲」です。
珈琲の豆知識ノートとして
産地や珈琲用語、道具のこと、ノート代わりにブログ記事にしていきます。
情報発信の場として
「地域情報」や「イベントの様子」などのレポートや情報発信に使います。
おんど珈琲は「珈琲を淹れることを通じて、地域の情報を発信」したい存在です。
また、日本全国各地のロースター、焙煎士の情報、イベントや地域の情報発信メディアとしても活動します。
屋号の由来
最後に、「おんど珈琲」と名付けた理由を。
長々と書いたこと、それを短い「おんど」という言葉にまとめました。
「恩」
ロースター、焙煎してくれた方、焙煎士さんが仕入れる業者さん、珈琲豆の栽培に携わる国や農園の人たちへの恩を大切にという思いを込めて。
多くの産地は赤道近くなので、行くことが困難です。
農園の方への感謝の気持ちと、仕入れ業者さんの努力、サードウェーブにより透明化された珈琲豆のルートを、バリスタの段階で止めてはいけないし、透明化するだけではなく、飲む人にも少しでも伝えていくことが、珈琲豆に携わって頂いている人たちへの「恩」だと思っています。
「温」
おんど珈琲を通じて、温かみのある、温もりのある珈琲時間を送ってもらえますように、との思いを込めて。
「音頭」
老若男女が口にしやすく声に出しやすい言葉、また日本人の誰もが聞き馴染みのある音楽のジャンル「音頭」、地域を連想させるような言葉を選びました。
おんど珈琲は、日本全国でおいしい珈琲を淹れる珈琲屋を目指します
今、特定の場所に店舗を構えるでもなく、コーヒートラックを所有している訳でもありません。
主旨はそのままに、今後事業形態が変わる可能性は有りえますし、更新は必要です。
重要なのは、「思い」。
これだけはブレずに、ブレそうになったら初心を思い出して、ゆっくりと活動を続けていけたらと思います。
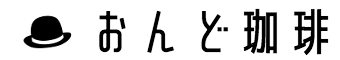
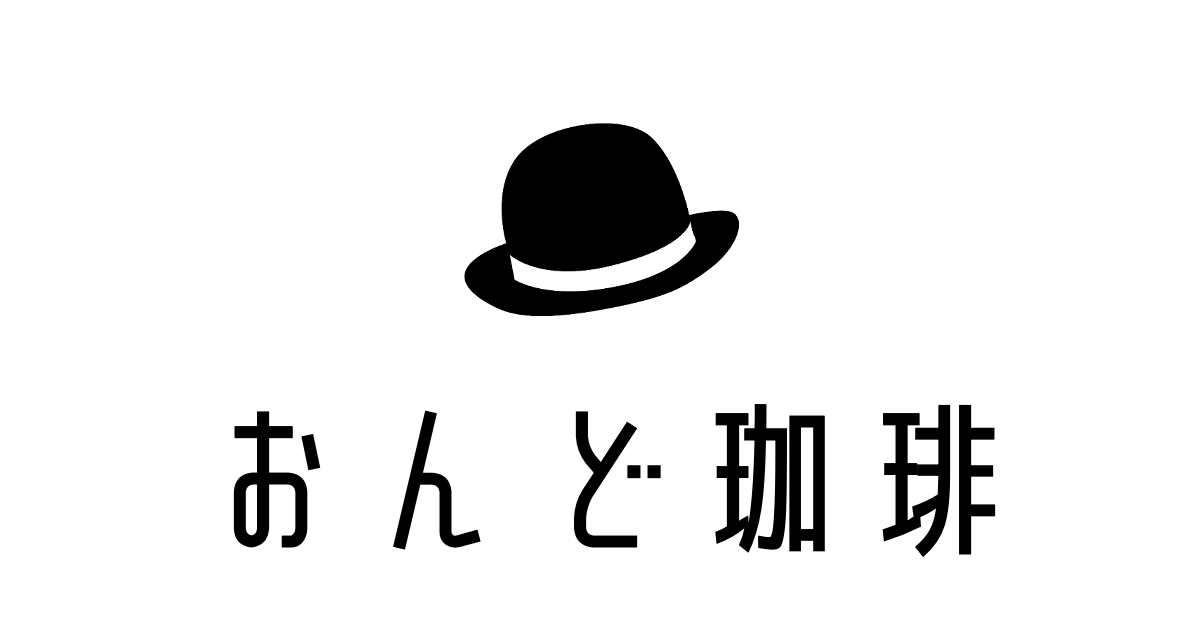
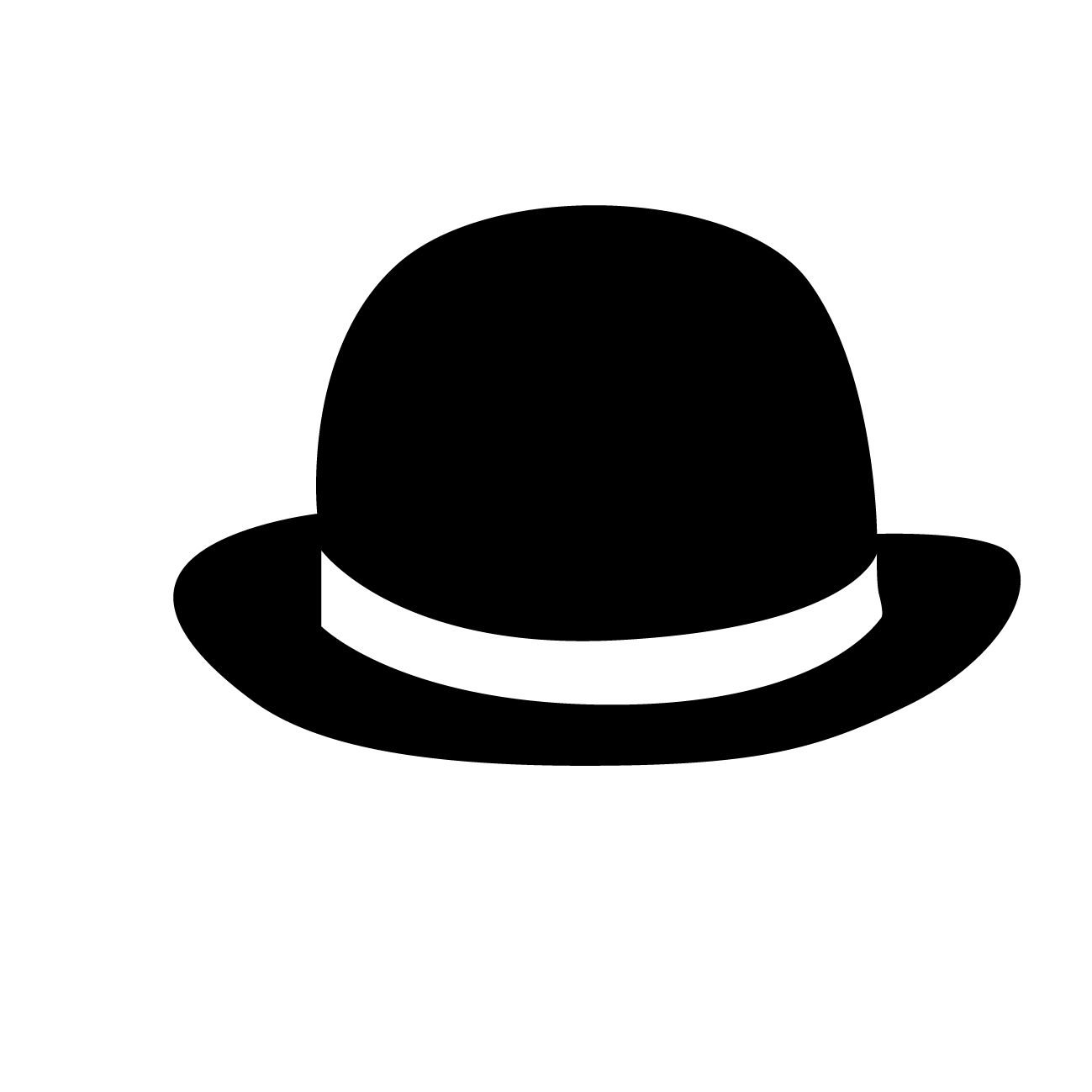

コメント