コーヒーのハンドドリップで、よくある議論。
それが「コーヒー豆をセットする前に。ペーパーフィルターを濡らすか、濡らさないか」です。
この濡らすという技術を「リンス」と呼ばれたりもします。

先に言っちゃうと、ぼくは濡らすことはしません。
コーヒーの淹れ方を調べているとペーパーフィルターを「濡らす派」と「濡らさない派」に分かれますよね。
でも、ぼくの中では「どちらでも良い」と思っています。
でも濡らすことによって、コーヒーの味や淹れ心地に変化があるのは確かです。
ペーパーフィルターは、濡らしても濡らさなくてもOK

さて、いきなり結論になりますが、濡らしても濡らさなくても味や香りに「大差」はありません。
なので「どちらでも良い」というのがぼくの考えです。
でも「それなら濡らさないほうが楽なんじゃないか?」となりますよね。
大差はないですが、少しの差はあります。
コーヒーを淹れ始める前に、ペーパーフィルターを濡らすとどうなるのかを、検証してみました。
ペーパーフィルターを濡らすと起こる5つのこと

ハンドドリップの蒸らしの前に、ペーパーフィルターを「濡らす」のと「濡らさない」のとでは、若干味に違いが出ます。
ペーパーフィルターに付いている「匂い」が取れる
ペーパーフィルターの匂いを、よく嗅いでみたら分かることです。
ペーパーフィルターには、若干匂いが付いています。
その匂いは、お湯で濡らすことで、元々の匂いを少し取ることが可能。
特に「無漂白の茶色のフィルター」は、匂いが分かりやすいです。
しかし、濡らさずにコーヒーを淹れても、出来上がりのコーヒーから「ペーパーフィルターの匂い」を感じることはないと思います。
本当に「微妙な香りの違い」が分かる人にとっては感じるのかもしれません。
でも、普通にコーヒーを飲んでいて「紙の匂いがする」ほど香ることはないでしょう。
ただし、ペーパーフィルターを剥き出しの状態で保存している人は注意。
「料理」や「生活臭」などの匂いが、ペーパーフィルターに染み付いている可能性があります。
保存場所を変えるか、もしくは「ジップロック」などに入れて保存しましょう。
ペーパーフィルター自体の「味」が取れる
ペーパーフィルターには、若干味が付いています。
試しに「ペーパーフィルターを濡らして落ちたお湯」と「普通のお湯」を飲み比べてみました。
本当に若干ですが、ペーパーフィルターの味が付いています。
ただし、これもコーヒーをドリップして飲んでも分からないレベルです。
ペーパーフィルターがドリッパーに「密着」する
ペーパーフィルターを濡らすと、フィルターがドリッパーに密着します。
これによって、コーヒーの淹れ心地が変わりました。
密着している分、ドリッパーからフィルターが「浮いている」感覚がないので、淹れやすいと感じました。
では、濡らすほうが良いのか?
それは一概には言えなくて、濡らさない場合の、ドリッパーとパーパーフィルターの間に「隙間」がポイント。
実はこの隙間、ちょっとした役割をしてくれています。
コーヒー豆にお湯を注ぐと、コーヒー豆が膨らみます。
この膨らみは、コーヒー豆の中にある炭酸ガスが抜けていっている証拠。
ドリッパーとペーパーフィルターの間の隙間は、その「炭酸ガスの抜け道」としての役割を持っています。
では、密着していることでどうなるでしょうか?
炭酸ガスの抜け道は「ドリッパーの上部のみ」になります。
ハンドドリップでは、炭酸ガスを上手に逃がしながら淹れることが、ポイントのひとつ。
ペーパーフィルターを濡らすことでドリッパーと密着してしまうのは、もしかしたらひとつのデメリットかもしれません。
ドリッパー内へのお湯の「注ぎやすさ」が変わる
ペーパーフィルターを濡らすと、ドリッパーとフィルターが密着。
それにより、お湯の注ぎやすさが少し変わります。
ハンドドリップの基本は、真ん中からお湯を注ぎ、ドリッパーの淵にはお湯をかけないこと。
ドリッパーとペーパーフィルターを密着させていたほうが、淵にかからないような「注湯」がしやすいです。
とはいえ、ハンドドリップに慣れていれば問題なし。
フィルターが密着していなくても、淵にお湯をかけずにドリップできます。
そのため、注ぎやすいと感じるのかどうかは個人差があると思います。
サーバーやドリッパーを「温める」ことができる
コーヒーをおいしく淹れるなら「サーバーやドリッパーをあらかじめお湯で温めておくこと」が、ひとつのポイント。
「ドリップしたコーヒー」と「ドリッパー、サーバー」の温度差を減らすためです。
ペーパーフィルターをお湯で濡らすついでに、ドリッパーとサーバーを温めることができます。
しかしもちろん、ペーパーフィルターをセットする前にお湯で温めることは可能。
なので、温めるために「濡らす」のは、ちょっと目的が変わってしまうのかな?と思います。
ドリッパーの種類によって「濡らす」か「濡らさない」を決めるのはアリ

ドリッパーの種類によって、ペーパーフィルターを「濡らす」か「濡らさないか」を決める、という方法もあります。
ドリッパーには数種類ありますが、まず「ハリオのV60」や「カリタ式」「コーノ式」は濡らす必要がないのでは?と個人的に思います。
理由は、ドリッパーの構造が「ペーパーフィルターと密着しないよう」になっているから。
上記のドリパーは、内側に「リブ」と呼ばれる溝があります。
これは、パーパーフィルターとドリッパーの間の隙間を作るためです。
メリタ式は濡らしても良いかも
ドリッパーの中でもメリタ式のドリッパーに関しては、お湯で濡らすのもアリかもしれません。
メリタ式のドリッパーは、ゆっくりとコーヒーを抽出することが特徴です。
お湯がドリッパーの内部に溜まりながら、小さなひとつ穴からじっくり抽出されていきます。
これは多くのドリッパーが「透過式」であることに対し「浸漬式」に近いと言える構造です。
そのためメリタ式ドリッパーは「最初から最後まで、お湯がドリッパーの中に溜まるように」ドリップするのが理想。
ペーパーフィルターを濡らすことでドリッパーと密着するので、メリタ式ドリッパーの良いところを引き出すことができます。
使うドリッパーごとに濡らす、濡らさないを決めるのも、楽しいかもしれませんね。
もちろん、これはぼくが考える一例。
ハリオのV60を濡らすのも、間違いではないと思います。
ハンドドリップは奥が深いから、いろんな方法を試してみましょう

ネットやYouTubeには、様々なハンドドリップの方法が紹介されています。
そんな中での方法のひとつが、ペーパーを濡らすか濡らさないか。
どちらのほうが良いと簡単に言い切ることはできませんが、コーヒーの味を微妙に左右することは確かです。
そこまで味を細かく追求できるのも、ハンドドリップの魅力のひとつではないでしょうか。
ハンドドリップはとても奥が深く、新しい情報がどんどん出てきています。
色々研究して、自分なりのハンドドリップのコツを掴み、おいしいコーヒーを淹れていきましょう。
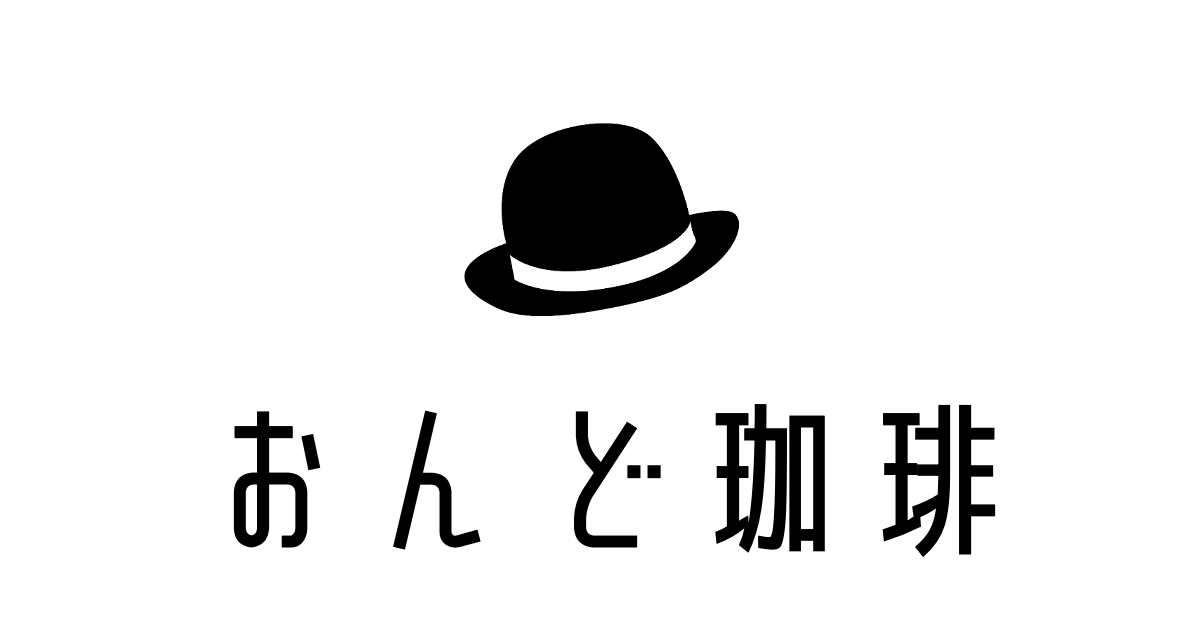





コメント