コーヒーをハンドドリップする時には、まず基本を押さえておくことが大切です。まず基本をマスターしておくことで、色々な淹れ方を楽しむことができます。
よく言われる「土手を作る」「真ん中にお湯を注ぐ」とは、なぜなのでしょうか?理由を知っておくことで、ハンドドリップのコツを理解することができます。
ハンドドリップのコツ【基本】

ハンドドリップは、とても奥が深いです。同じコーヒー豆を使っていても、人によって味に違いが出てきます。お湯の温度、コーヒー豆の量、お湯を注ぐスピード…それぞれが少し違うだけで、出来上がりのコーヒーの味は変わります。
まずはハンドドリップで淹れるコーヒーの基本を押さえておきましょう。
ハンドドリップのコツ:ドリッパー内に土手を作る

ハンドドリップはお湯をドリッパーに注いでコーヒーを抽出しますが、その際にドリッパーの淵に土手を作ってやることがポイントです。
土手は、コーヒーの成分をうまく抽出するための濾過層の役割をしてくれます。以下、土手のことを濾過層と表現します。
濾過層を作ってやる
ドリッパー内のコーヒーの粉にお湯を注ぐと、もこもこと膨らんでいきます。真ん中にお湯を注ぐことによって、段々とドリッパーの淵にコーヒーの粉で作られた土手ができます。その土手が、濾過層の役割を果たしてくれるのです。
濾過層が作られていない場合、お湯がダイレクトにサーバー内に落ちてしまいます。コーヒーの粉全体にお湯を行き渡らせたい気持ちもありますが、その必要はありません。
コーヒーは、ひとつひとつの粉から抽出するイメージではなく、15グラム(1杯あたり)のコーヒー豆の総力戦でコーヒーを淹れるものです。
濾過層にあるコーヒーの粉に直接お湯をかけなくても、コーヒーの成分は抽出されています。むしろコーヒーの成分を十分に抽出し、薄くならないようにするために濾過層、土手は必ず必要になります。
ドリッパーの淵にある濾過層にお湯をかけると、コーヒーの成分を余すところなく抽出できると考えがちですが、この箇所は十分な量のコーヒーの粉がない場所です。そのため、逆に濃度の薄いコーヒーが抽出されてしまいます。
ハンドドリップのコツ:真ん中にお湯を注ぐ

ハンドドリップでは、真ん中からお湯を注ぐことがポイントです。前述したように、濾過層を崩さないようにするためでもあります。
「の」の字を書くようにお湯を注ぐ理由
よく言われる「の」の字を書くようにするという意味は、ドリッパー内の土手を均一に保つためです。均等な濾過層を作ってやることで、コーヒーの成分はまんべんなく抽出されます。
例えばじゃばじゃばとお湯を注いだとしても、コーヒーの成分は抽出されます。しかしコーヒー豆には雑味も必ず含まれているので、その雑味までサーバーに落としてしまうことになります。
丁寧に「の」の字を書くようにお湯を注ぐと、ドリッパー内のコーヒーの粉はきれいな濾過層が保たれます。
ドリッパー内のコーヒーの層を、できるだけきれいにするようなイメージでお湯を注ぐことがポイントです。
ハンドドリップのコツ:透過式であることを活かす

ハンドドリップは「透過式(とうかしき)」と言われる抽出方法です。透過式とはコーヒーの粉にお湯を通すことでコーヒーの成分を抽出する方法のこと。コーヒーの細胞の隙間にお湯が通ることによって、コーヒーの成分は抽出されます。
浸すのではなく濾(こ)す
透過式の逆は「浸漬式(しんせきしき)」です。つまり、浸すことによってコーヒーの成分を抽出します。浸漬式の場合、コーヒーの成分を余すところなく抽出してくれます。しかし、余すところなくということは、雑味なども抽出してしまうということです。
濾過層を作らないようにお湯を注いでコーヒーを淹れるということは、透過式よりも浸漬式に近い抽出方法と言えます。
透過式の良いところは、雑味を出さないようにコーヒーを抽出できることです。例えばドリッパー内のコーヒーの粉全体に浸すようにお湯をかければ、それは透過式の良いところを活かしきれていないということになります。
上手に濾すことによって、クリアな味わいを出すことができる淹れ方が透過式です。もちろん浸漬式にも良いところがあり、個人の好みにもよるので一概に良し悪しを判断することはできません。
しかしハンドドリップで透過式の抽出方法をしている限りは、お湯を浸すよりも通すことをイメージするようにしましょう。
ハンドドリップのコツ:最後まで落としきらない

ハンドドリップの最後は、ドリッパーに溜まったお湯を全て落としきらないことがポイントです。ドリッパー内にお湯が溜まっている状態で、抽出をやめましょう。
その理由は、ハンドドリップで淹れるコーヒーは最初の一滴が1番濃く、だんだんと成分が薄まっていくという特徴があるからです。
コーヒーのおいしい成分は段々減っていく
コーヒーの成分の出方は、お茶や紅茶などとまったく逆です。お茶や紅茶が最後のなればなるほど濃くなることに対し、コーヒーはドリップの後半になるにつれて段々と薄くなっていきます。
またそれと同時に、雑味も抽出されるというデメリットがあります。コーヒーにはたくさんの成分が含まれていますが、全てが同じタイミングで抽出されるということはありません。
おいしい成分が先に出るのに対し、雑味は後半になるにつれて段々と出てきます。そのため、ドリッパー内のお湯を最後まで落としきってしまうと、雑味まで全て落としきってしまうということになります。
おいしく淹れるポイントとしては、最初はゆっくりと注ぎ、目的の抽出量に近づいたら淹れるスピードを早めることです。そうすることによって、濃度の調整や雑味を落とさないようにすることができます。
コーヒー豆には必ず雑味が含まれている

どんなに良質なコーヒー豆にも、必ず雑味は含まれています。きつすぎる酸味や、渋み、えぐみなどです。高価なコーヒー豆でも同じことが言えるし、スペシャルティコーヒーだからといって雑味がゼロなことはありえません。
良いコーヒーでもある程度は雑味があるもの
スペシャルティコーヒーの普及によって、コーヒー豆の品質は格段に上がっています。そのため、雑味自体が減っていると考えることもできます。
それでも淹れ方によって雑味が入ってしまうのは、やはり基本を押さえていないから、ということになります。どんなに良いコーヒー豆を使っても、雑味は必ず含まれており、それをサーバー内に落とさないようにすることが、ハンドドリップのポイントと覚えておいてください。
濾過層のコーヒー豆はどういう役割?

ドリッパーの構造上、真ん中に1番コーヒーの粉が集まります。深さがあるので当然のことですよね。特にハリオのV60ドリッパーやコーノ式ドリッパーは円錐型なのでわかりやすいと思います。そのため、真ん中にお湯を注ぐのは理に適っていると言えます。
例えば濾過層のコーヒーの粉にお湯をかけると、確かに全てのコーヒーの粉にお湯が直接行き渡ります。しかし、実はコーヒーの粉にお湯を注いだ段階で、お湯はどんどん周りのコーヒーの粉に移動していっています。
濾過層がないところには、十分な量のコーヒーの粉がありません。そのため、コーヒーの成分を抽出しきれないまま、サーバー内に落ちてしまいます。濾過層があることによって、濃度の高いコーヒーを淹れることができるのです。
もちろん濃度の高いコーヒーが良いコーヒーと言い切ることはできませんが、濾過層があることによってしっかりした味わいを出すことができると覚えておきましょう。
500円玉程度の大きさまでお湯を注ぐ理由は?

前述したように、お湯はコーヒーの粉同士の間でだんだんと広まっていきます。そのため真ん中に注ぐと、ある程度広まっていってくれるのです。
500円玉程度の大きさでお湯を注げば、周りの濾過層を崩さず、さらにドリッパー内の粉全体に少しずつお湯が広がっていきます。
全体にお湯をかけずとも、お湯を行き渡るものです。ドリッパー内にお湯を注ぐと、遠心状にお湯が広がっていきます。そのため、500円玉程度の大きさで十分ということになります。
お湯が広まる仕組みは以下の通りです。
まず蒸らしの段階で、コーヒーの粉全体にお湯が行き渡ります。お湯が行き渡ることによって、コーヒーの粉ひとつひとつが開いていき、お湯の受け渡しがスムーズになります。そうすることで、濾過層にもうまくお湯が伝わっていくという仕組みです。
浅煎りのコーヒー豆で濾過層がうまく作れないときは?

浅煎りのコーヒー豆は、うまく膨らんでくれずに濾過層が作りにくい場合があります。特に極端な浅煎りの場合、ドリッパーの底にコーヒーの粉が溜まってしまい、ドリッパー内に水たまりができてしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、基本から少し外れた淹れ方をしたほうが良いかもしれません。コーヒー豆や焙煎度によって淹れ方を変えられるようになれば、ハンドドリップに随分慣れていると言えるでしょう。
ハンドドリップは基本をまずマスターしましょう

ハンドドリップは、まず基本をマスターすることから始めましょう。最近では、コーヒーの粉にまんべんなくかけるという淹れ方もありますが、その方法だと透過式ではなく浸漬式になってしまいます。
とはいえ、その淹れ方があながち間違っているということは言えません。コーヒー豆の特徴や個性を出すためには、その淹れ方のほうが良いという場合もあります。
まずは基本の淹れ方をマスターしたり、ドリッパー内のお湯の動きを理解することで、自分流にアレンジすることができます。何事も基本が大事と言いますが、まずはお手本のようなハンドドリップをマスターしてみるようにしましょう。
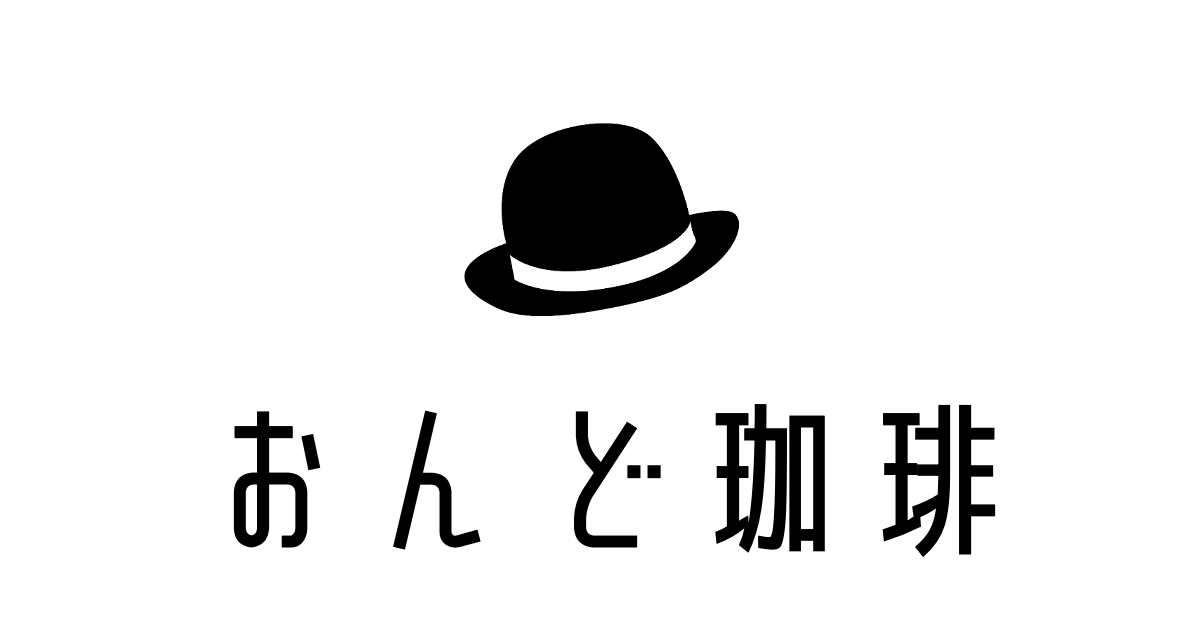








コメント